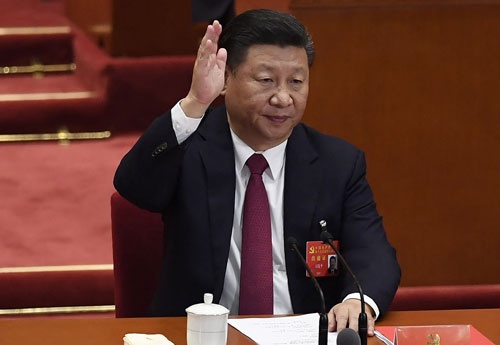
9月29日、日本と中国は国交正常化50年を迎える。当時、中国にとって「見上げる」存在だった日本は、今や「見下ろす」存在となった。それはなぜか。なぜ中国経済が飛躍的な成長を遂げる隣で、日本は劣化の道を歩んだのか。日本はこれから中国といかに付き合っていくべきか。日中関係と米中関係を長年研究してきた、日本総合研究所の呉軍華・上席理事に聞く。
(聞き手:森 永輔)
日本と中国の関係はこの50年間、中国から見てどのように推移してきたのでしょうか。
呉軍華・日本総合研究所上席理事(以下、呉氏):1972年に日本と国交を正常化した中国にとって、日本は仰ぎ見る存在でした。「美しいお月様」を見る感覚に近かったと思います。私は80年代半ばに東京大学の大学院に留学しました。アジアにはアジア的な近代化モデルがあるはずで、その神髄を日本で学べると思ってのことでした。
ところが、中国がその後に経済成長を始め、政治的にも軍事的にもパワーを大きく増強するにつれて、視線の角度は「見上げる」から「水平」に、そして「見下ろす」と変わってきました。上から目線に変わったのは、2008年のリーマン・ショックで傷ついた世界経済の回復に大きな役割を果たし、10年にGDP(国内総生産)で日本を追い抜いた頃からだと思います。中国は大きな自信を身に付けました。

グローバル化で伸びた中国、縮んだ日本
中国はなぜ今日の経済成長を実現できたのでしょうか。
呉氏:それは、冷戦終結と軌を一にしてグローバル化が始まったからだと考えます。グローバル化の本質は経済学でいう「比較優位」の追求です。安い賃金と緩い環境・労働規制という比較優位を持つ中国に、西側の企業はこぞって生産拠点を設けました。それゆえ、中国は「世界の工場」になることができたのです。
この外国からの投資を呼び込む準備として、鄧小平が推進した改革開放政策が大きな役割を果たしました。改革開放政策が重要だったことは論をまちません。中国は海外資本を集めるため、その政治・経済資源を集中投入しました。深圳などに経済特区を設置したのはその一例です。
他方、グローバル化は米国や日本など西側諸国の経済と政治にはネガティブに作用しました。これらの国の企業は安い賃金と低い法人税を求めて海外に出ていきました。それに伴う賃金上昇の失速などの痛手を被ったのは中間層です。「一億総中流」を実現していた日本は、この影響を国全体で受け停滞を余儀なくされました。
米国では、ラストベルト地帯を中心にそれまで豊かな生活を満喫していた労働者層が大きな不満を抱えることになりました。保守の共和党とリベラルの民主党の間で振り子のように政権を回しつつバランスを取っていた国内政治の基盤も大きく崩れた結果、社会が大きく分断した。これがトランプ現象となって爆発したのです。
ちなみにグローバル化と国際化は似て非なるものです。1980年代に進んだ国際化は、自由と民主主義という同じ価値観を持つ国々による市場統合でした。これに対してグローバル化は、中国を含む、異なる価値観と政治体制を持つ国を同じ経済システムの内側に抱え込む形で進んできました。
異なる価値観と政治体制のもとで比較優位の競争をした場合、民主主義国は決してこの競争を制することができません。他方、非民主主義国は、こうした競争を制することでパワーが増強するにつれて、自らの主義主張をグローバルに展開しようとするようになります。これこそが米中の対立、ひいては日本を含む西側諸国と中国との関係悪化を招いた最大の原因だと思います。
米国は第1期オバマ第1次政権まで中国に対していわゆるエンゲージ政策を取ってきました。中国で経済が成長すれば民主化が進み、西側の価値観を受け入れるようになる、との期待に基づく政策です。しかし、中国がこの路線に進むことはありませんでした。米国は第2期オバマ政権でエンゲージ政策の限界を意識し、トランプ政権のもとで転換しました。ちなみに、バイデン政権は中国を「最も重大な競争相手」と位置付けています。
中国共産党を日米の民主主義が救った
中国の今日の成長は、日本が戦後に提供した技術協力やODA(政府開発援助)があったればこそ、との見方が日本の一部にあります。
呉氏:中国の成長はグローバル化があったからこそのもの。ただし、グローバル化が始まるまでの期間に、日本や米国が中国共産党を支援したことも要因の1つにあります。

第2次世界大戦後、毛沢東率いる中国共産党と蒋介石率いる国民党が中国で内戦を展開しました。前者にはソ連、後者には米国がそれぞれついていた、との構図で語られることが多くあります。ですが、実は、米国が中国共産党に実質的に貴重な支援をしました。内戦の帰趨(きすう)を大きく決めた場所は中国東北地域、それまでの満州でした。国民党軍は、共産党軍を朝鮮半島との境まで追い詰め、このままいけば国民党軍が勝利するところでした。ところが、進軍する国民党軍に米国が待ったをかけたのです。これによって息を吹き返した共産党の林彪軍は反攻に転じました。この結果、国民党軍は敗退し、台湾に逃げることになりました。
1989年に天安門事件が起きたとき、国際社会から孤立した中国に最も早く手を差し伸べたのは日本でした。同事件が起きた6月4日、まさにその日の時点で日本政府は、主要7カ国(G7)による制裁を拒否し、融和的な対応を取る方針を固めていました。2020年に公開された外交文書で、この点が明らかになっています。天安門事件が起きた1年後には、事実上の凍結していた第3次円借款を解除しています。その一方でブッシュ政権(当時)も事件の直後に、中国を厳しく非難しつつも中国に密使を派遣しました。
なぜ米国は中国内戦において、イデオロギー的に対立する中国共産党を結果的に救ったのでしょうか。なぜ日本は、天安門で民主派を弾圧した中国共産党への制裁に消極的だったのでしょうか。それは民主主義が「偽善」を内包しているからです。
1980年代までの国際化の恩恵を受けて成長し、次なる巨大市場を欲していた日本の目に、中国市場は大きなチャンスに映りました。改めて強調するまでもありませんが、欧米諸国も事情は同じでした。つまり、日本も欧米の民主主義諸国も、人権保護の普遍性を訴えつつも、安い生産コストや製品市場という経済的な利益に惑わされ、他国で起きている人権侵害をあくまでも他国の事情とし、実質的に無視したのです。
イデオロギー的に相容れない関係であっても、米国が中国共産党に融和的だった原因は他にもあります。実質的にキリスト教の国である米国には、人、特に弱者・貧者を救うのを使命とする人が多くいます。リベラリストはとりわけ人種やジェンダーの平等を求めます。こうした米国人にとって、30年代、独裁体制の打倒と平等社会の実現を訴え、辺ぴで貧しい延安などで活動している中国共産党の人々は、イデオロギー的に対抗すべき相手というよりも、同情し、救い上げたい対象でした。
顔こそ中国人であるものの、その身なりや振る舞いは欧米人と変わらない蒋介石や妻の宋美齢よりも、延安の貧しい農民と変わらぬような毛沢東や、ベルトに銃を差して勇ましく戦っているように見える共産党の女性兵士の方がずっと魅力的に映ったのでしょう。『中国の赤い星』という著書で中国共産党を国際社会にポジティブに紹介した米国のジャーナリスト、エドガー・スノー氏は、米国のこうした面を代表する1人でした。
民主主義は宥和という名の「DNA」を抱えている点も忘れてはいけません。第2次世界大戦のときも、英国やフランスはぎりぎりの段階までドイツとの武力衝突を避けようとしました。そして米国もぎりぎりまでドイツや日本との正面衝突を避けようとしていた。
そして、どうしても戦わなければならない局面に直面したとき、当面の「悪」に対処するため、民主主義の原理原則を無視して潜在的な「悪」にあえて手を差し伸べたのです。ドイツに対抗するためソ連を強大な存在に育てました。そして、巨大化したソ連と戦うため、今度は中国を支援する方に動きました。こうしたパターンを繰り返してきたのです。
英国で首相を務めたチャーチルが民主主義を「最悪の政治形態」と呼んだのは、決して間違いではなかったと考えます。
米中対立が今後も続く2つの理由
米中の対立は今後どうなっていくでしょう。
呉氏:グローバル化が生み出した米中対立は、今後も悪化の一途をたどります。理由は2つ。1つは、米国の対中感情の悪化が国民レベルまで大きく浸透していることです。ペロシ米下院議長の台湾訪問はその象徴です。「台湾を見捨てない」「米国は台湾とともにある。米国は台湾と団結する」。米下院議員は2年ごとに国民が直接投票で選びます。そのトップである議長の発言は米国の民意の表れです。
今後、バイデン政権が継続しようが、トランプ氏が復活しようが、他の誰が大統領になろうが、米政権はこの民意に従わないわけにはいかないでしょう。
第2の理由は、中国共産党政権が民主化に進む可能性が極めて低いことです。
香港や台湾は民主化を果たしました。中国にも可能性があるのではありませんか。
呉氏:台湾の民主化は、中国の脅威にさらされていたという特殊事情が大きく作用しました。蒋介石の後を継いだ息子・蒋経国は、民主化しなければ米国の支援が得られなくなることを理解していました。それゆえ民主化にかじを切ったのです。今の中国に、当時の台湾にとっての中国のような脅威は存在しません。
さらに、中国共産党による現在の統治の形態は、秦の始皇帝以来、中国が取ってきた政治体制と非常に高い親和性を持ちます。秦による統治は儒教よりも、法家の思想に基づくものでした。
法家について、百科事典「マイペディア」(平凡社)は次の趣旨を説明しています。「君主と人民の利害は相反する。人民を法で規制すべき」「臣下を賞罰をもって自在に操縦すべき」「法の権威を保つべくいっさいの批判を封じるべき」
呉氏:中国共産党政権は、この法家思想に基づく統治を背骨に据え、共産主義の衣をまとったものと評価できます。共産主義は、その組織力をもって統治をより強固なものにします。この伝統と組織力ゆえに、中国共産党流の統治が簡単に変わることはありません。
日本が取るべき道は「富民強国」
日中国交正常化から50年を経る間に大きく変身した中国と、日本はいかに付き合っていくべきでしょうか。
呉氏:答は簡単です。実力を付け、中国の「上から目線」を「水平」に戻すのです。
政治と安全保障の面では、戦争を抑止する力を高めることが必要でしょう。台湾、東シナ海、南シナ海--。日本、そしてその周辺の平和を守る力を強化する。
経済の面では、中国を含め海外市場に頼らなくても自律的に成長できる経済をつくり上げるべきです。所得が伸び悩み、世界経済における日本経済の地位が大きく低下しました。一方、米中関係も日中関係も元に戻るのが困難な状況になっています。今は平時ではなく、非常時だとの認識が必要でしょう。経営者にとって、もはや経済的な合理性だけでビジネスを考えてよい状況ではありません。
グローバル化への未練があるかもしれませんが、いやでもその限界を認めざるを得ないときです。デカップリング(分断)も避けて通ることは難しいと認識すべきでしょう。
【5/16締切!】春割・2カ月無料 お申し込みで…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号12年分のバックナンバーが読み放題
この記事はシリーズ「森 永輔の世界の今・日本の将来」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。












